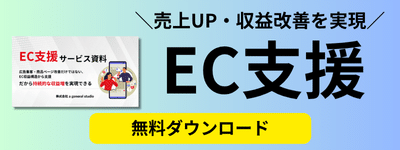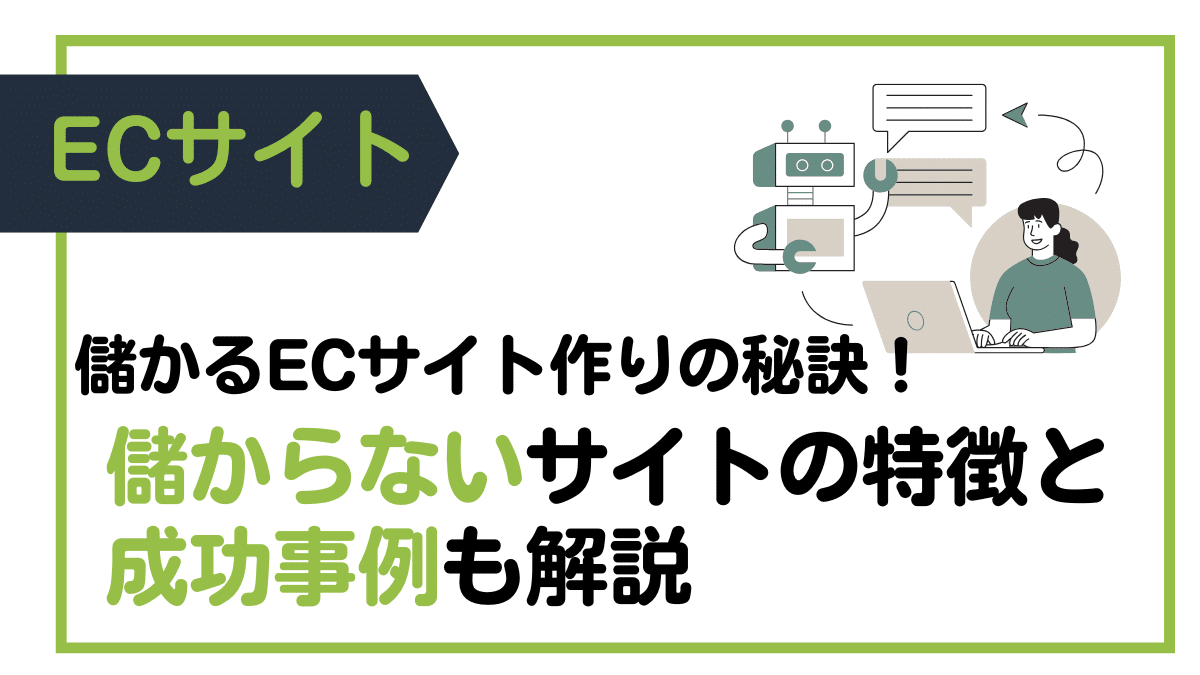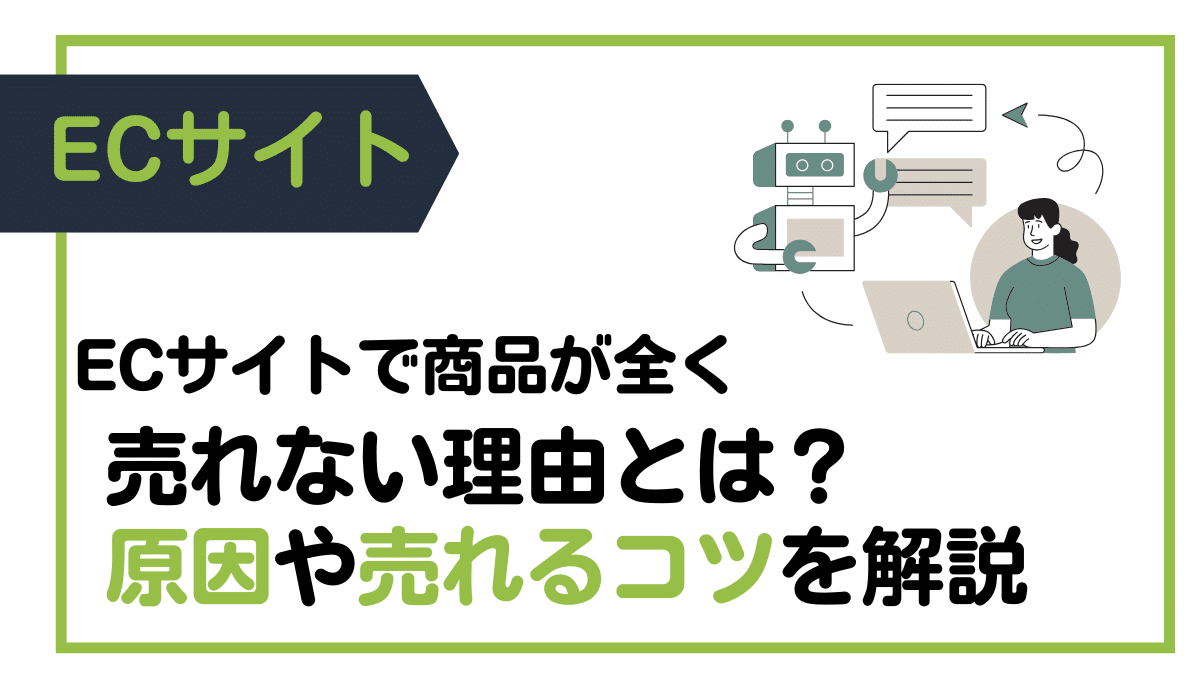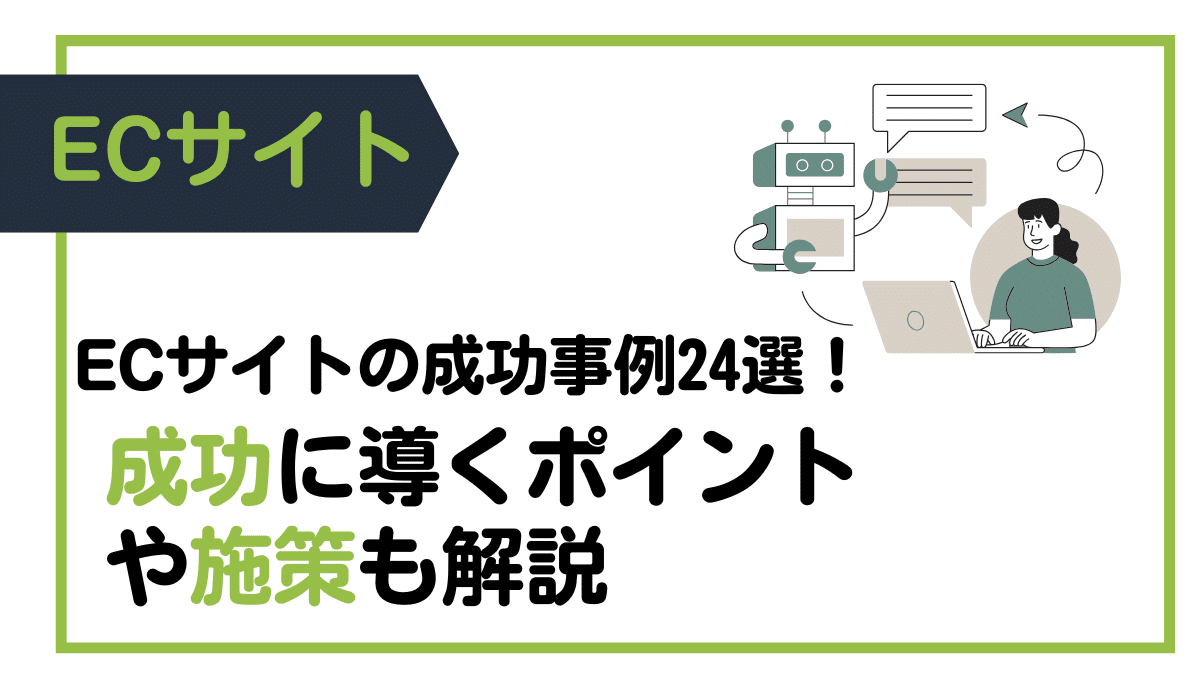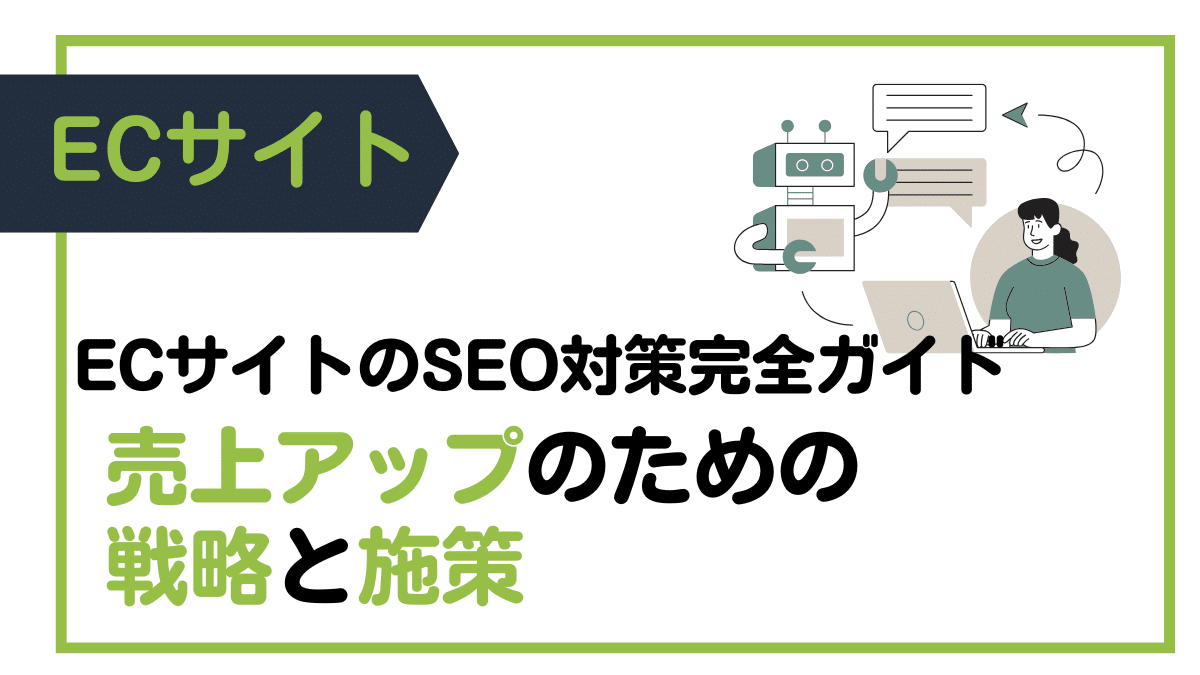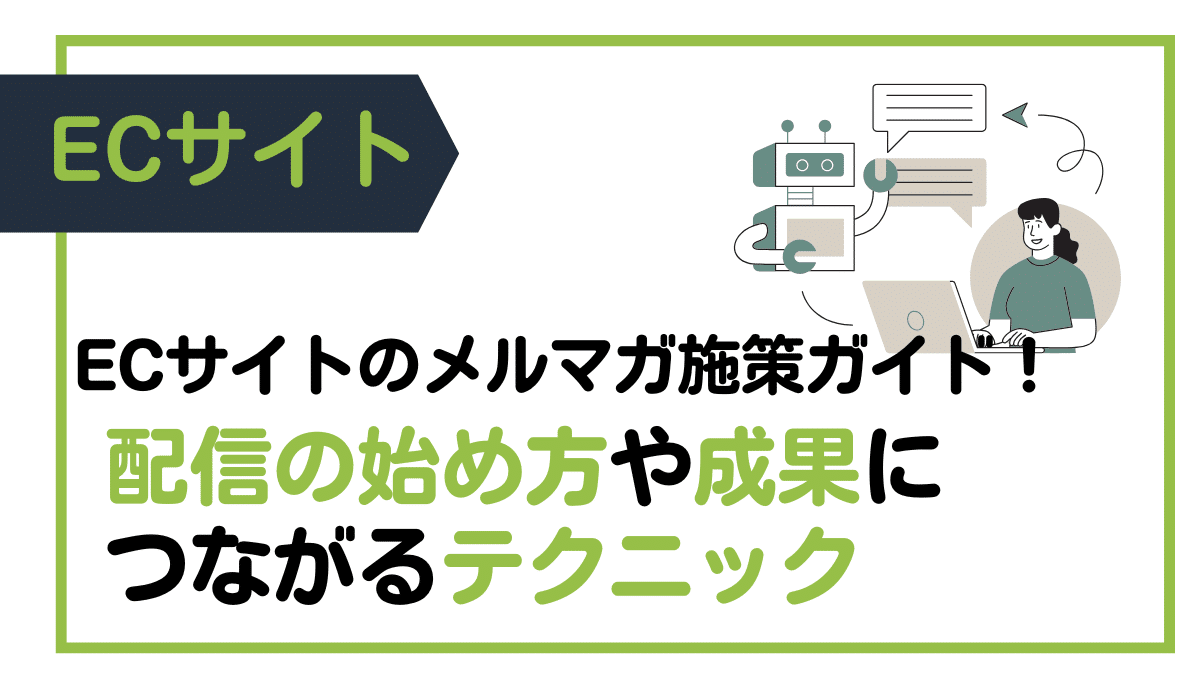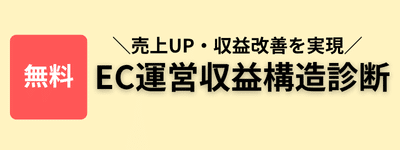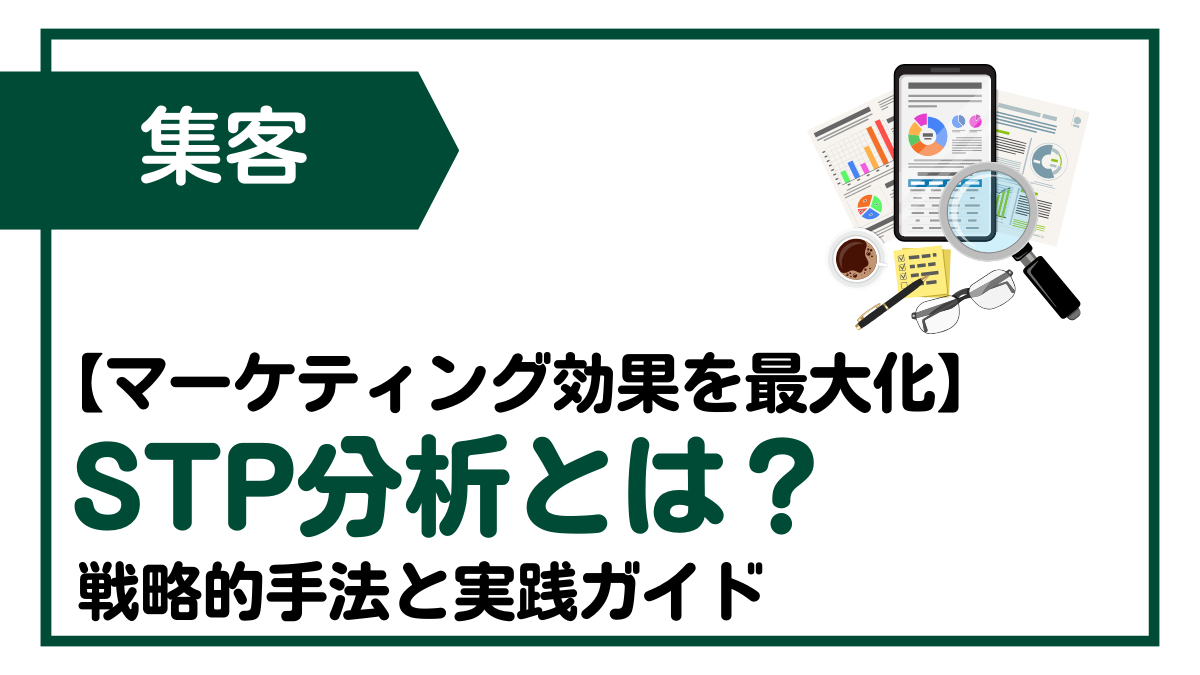
- EC
STP分析とは?マーケティング効果を最大化する戦略的手法と実践ガイド
目次
STP分析とは、マーケティング戦略を立案するための体系的なフレームワークです。
Segmentation(セグメンテーション)、
Targeting(ターゲティング)、
Positioning(ポジショニング)
の頭文字からなり、市場を細分化し、最適なターゲットを選定し、効果的に自社製品を位置づけるプロセスです。
現代のビジネス環境では「すべての人に向けた」マーケティングは効果的ではなく、限られた予算で成果を出すには明確なターゲット設定と差別化戦略が不可欠です。
日本企業の約60%はSTP分析を十分に活用できておらず、マーケティング効果を最大化できていないという調査結果もあります。
この記事では、STP分析の基本概念から実施手順、活用事例まで実践的な情報をお届けします。
STP分析の基本概念と全体像
Segmentation(セグメンテーション)とは
セグメンテーションとは、市場を特定の基準に基づいて、似た特性や行動パターンを持つ顧客グループに分ける作業です。
これは市場全体を小さなグループに分割するアプローチです。
セグメンテーションの基準には4つのカテゴリーがあります。
地理的セグメンテーション(地域、都市規模など)、
人口統計的セグメンテーション(年齢、性別、所得など)、
心理的セグメンテーション(価値観、ライフスタイルなど)、
そして行動的セグメンテーション(使用頻度、購買パターンなど)
です。
効果的なセグメンテーションのポイントは、セグメントが測定可能、アクセス可能、十分な規模があり、差別化可能で実行可能という条件を満たすことです。
Targeting(ターゲティング)の重要性
ターゲティングとは、セグメントで分割した市場から、自社のリソースや強みを活かせる最も魅力的なセグメントを選択するプロセスです。
限られたリソースを効果的に活用するために焦点を絞ることが重要です。
ターゲティングでは、市場規模と成長性、競合状況、自社の強みとの適合性、収益性などを基準にセグメントを評価します。
大きな市場規模のセグメントでも競合が多い場合は、競合の少ないニッチセグメントを選ぶ方が効果的な場合もあります。
ターゲティング戦略には、
集中戦略(単一セグメントに集中)、
差別化戦略(複数セグメントに異なるアプローチ)、
無差別戦略(市場全体に単一戦略)
の3つがあります。
現代の多様化した市場では差別化戦略が有効なケースが多いでしょう。
こちらの記事でも詳しく解説していますので、合わせて参考にしてください。
Positioning(ポジショニング)の戦略的意義
ポジショニングとは、選定したターゲットセグメントの顧客の心の中に、自社の製品やサービスを明確かつ望ましい形で位置づける戦略です。
「なぜ顧客が自社製品を選ぶべきか」という価値提案を明確にします。
効果的なポジショニングは、ターゲット顧客のニーズと価値観を理解し、競合との差別化ポイントを持ち、一貫したメッセージで伝達される必要があります。
ポジショニングマップは2つの軸(例:価格と品質)を設定し、その空間内に自社と競合を配置することで、市場における位置づけを明確にするツールです。
ポジショニングの例には
「最高品質のプレミアムブランド」
「最もコストパフォーマンスに優れた選択肢」
「初心者向けの使いやすいサービス」
などがあります。
重要なのは自社の強みと顧客ニーズに合致し、競合と差別化できることです。
STP分析の実施手順と具体的な方法
市場セグメンテーションの実践的アプローチ
効果的な市場セグメンテーションは、現状の市場と顧客の深い理解から始まります。具体的な実施手順は以下の通りです。
まず社内外のデータ収集と分析から始めます
既存顧客データ、市場調査レポート、競合分析、アクセス解析データなどを収集します。
日本では総務省の「家計調査」や経済産業省の「電子商取引に関する市場調査」なども参考になります。
次にセグメント基準を選定します。
BtoC市場では年齢や性別、ライフスタイルが一般的ですが、BtoB市場では業種や企業規模などが重要です。
例えば健康食品市場では「健康意識の高い40代以上女性」「筋トレを行う20〜30代男性」といったセグメントが考えられます。
その後、各セグメントのプロファイリングを行い、規模、成長性、行動特性、ニーズなどを分析します。
最後に各セグメントが「測定可能」「アクセス可能」「十分な規模」「差別化可能」「実行可能」の条件を満たしているか評価します。
ターゲットセグメントの選定手法
セグメントで市場を分割したら、次はどのセグメントをターゲットとするかを選定します。
この選定プロセスはビジネス成長に極めて重要です。
まず各セグメントの魅力度評価を行います。
市場規模、成長率、収益性、競合状況などの基準で評価します。
各基準にスコアをつけ、重み付けを行った上で総合点を算出するマトリクス評価が有効です。
例えば市場規模と成長率のバランスを自社の経営戦略に応じて判断します。
次に自社の強みとの適合性を評価します。
技術力や価格競争力などの自社の強みが、各セグメントのニーズにどれだけマッチしているかを評価します。高品質な製品提供が強みなら、品質重視のセグメントが適しています。
さらに競合状況も分析します。
競合の少ないブルーオーシャン市場や、競合がいても自社の強みで差別化できるセグメントが望ましいです。
最後に総合的な判断で、短期・長期のビジネス目標に最も貢献できるセグメントを選定します。
こちらの記事でも詳しく解説していますので、合わせて参考にしてください。
効果的なポジショニング戦略の構築
ポジショニングは、選定したターゲットセグメントの心の中に自社の製品やサービスをどう位置づけるかを決定する重要なステップです。
効果的な戦略構築には以下の手順が有効です。
まずターゲット顧客を深く理解します。
顧客が何を重視し、どんな問題を抱え、どんな価値を求めているかを顧客インタビューやアンケート調査などで探ります。
例えばあるスキンケアブランドは30代女性への深層インタビューで「効果は期待するが刺激の強い成分は避けたい」といった本音を引き出しました。
次に競合分析とポジショニングマップ作成を行います。
競合のポジショニングを分析し、2つの重要な軸(価格と品質など)でマップを作成して競合が手薄な「空白領域」を特定します。
続いて差別化ポイントを明確化します。
自社の強みと顧客ニーズを照らし合わせ、機能面と感情面の両方を考慮した差別化ポイントを特定します。
これは顧客にとって重要で、競合より優位性があり、長期的に維持可能である必要があります。
そしてポジショニングステートメントを策定し、すべてのマーケティング活動に一貫して反映させます。
STP分析に基づくマーケティング戦略の展開
4Pフレームワークへの落とし込み
STP分析で明確になったターゲットセグメントとポジショニングを具体的なマーケティング施策に落とし込むには、4Pフレームワークが有効です。
Product(製品)、
Price(価格)、
Place(流通)、
Promotion(プロモーション)
の4要素をSTP分析の結果に基づいて最適化します。
Productに関しては、ターゲットのニーズとポジショニングに合致した製品開発が重要です。
例えば「忙しいビジネスパーソン向けの時短調理キット」というポジショニングなら、準備時間の短さ、調理の簡便さ、栄養バランスを重視した製品設計が必要です。
Priceは、ターゲットの価格感度とポジショニングに基づく戦略が重要です。
プレミアムポジショニングなら高価格戦略、コストパフォーマンス重視なら中価格帯での価値訴求が適切です。
価格設定には競合分析、コスト分析、顧客の支払い意欲調査を組み合わせると効果的です。
Placeは、ターゲットの購買行動に合わせた流通チャネル選択が重要です。
現代では、オンラインとオフラインの適切な組み合わせが求められます。
例えば「デジタルネイティブな20代女性」をターゲットとしたアパレルブランドは、SNSとECを中心に体験型実店舗を主要都市に限定出店するという戦略が効果的です。
Promotionは、ターゲットの情報接触習慣とポジショニングに合わせたコミュニケーション戦略が重要です。
メッセージ内容、トーン、メディア選定など全ての要素がターゲットとポジショニングと一致している必要があります。
4Pの各要素は相互に関連しており、一貫性を持って最適化することが重要です。
デジタルマーケティングにおけるSTP分析の活用
デジタル技術の発展により、STP分析はより精緻かつ効率的に実施できるようになりました。
特にデジタルマーケティングでは、データに基づく詳細なセグメンテーションとパーソナライゼーションが可能です。
デジタル環境でのセグメンテーションでは、従来の基本属性に加え、行動データ、購買履歴、エンゲージメントデータなど詳細で動的なデータを活用できます。
例えばGoogleアナリティクスを活用すれば「初回訪問でニュースレター登録したが購入に至っていないユーザー」などの詳細なセグメントを特定できます。
ターゲティングにおいては、オンライン広告プラットフォームの進化により細かな条件設定が可能です。
Google広告やMeta広告などで年齢、性別、興味関心、行動履歴などの条件を組み合わせ、精密にアプローチできます。
ポジショニングの実装においても、ウェブサイトやアプリの設計、コンテンツ、ユーザー体験などを通じて一貫したポジショニングを表現できます。
A/Bテストを活用すれば、どのメッセージやデザインが最も響くかを科学的に検証することも可能です。
成功事例として、あるECサイトは「初回購入後30日以内に2回目の購入をする顧客はロイヤル顧客になる確率が5倍高い」という分析結果に基づき、初回購入者向けの特別オファーを実施し、2回目購入率を42%向上させました。
こちらの記事でも詳しく解説していますので、合わせて参考にしてください。
STP分析の継続的な見直しと改善
STP分析は一度実施して終わりではなく、市場環境の変化や自社の成長に合わせて継続的に見直し、改善していくことが重要です。
まず、定期的なデータ収集と分析サイクルを確立します。
四半期や半期ごとに市場動向、顧客行動、競合状況などの最新データを収集し、現在のSTP戦略の有効性を検証します。
セグメントの規模や成長率の変化、ターゲットニーズの変化、競合ポジショニングの変化などを定点観測します。
次にKPI(重要業績評価指標)の設定と定期的なモニタリングを行います。
セグメントごとの売上、顧客獲得コスト、顧客生涯価値、市場シェアなどを測定し、目標達成度を評価します。
顧客フィードバックの継続的な収集も重要です。
アンケート、カスタマーサポートデータ、SNS分析などから顧客の声を集め、自社ポジショニングが正しく認識され、ニーズを満たしているか検証します。
また、新しいセグメントへの試験的なアプローチも効果的です。
市場の変化に応じて新たなセグメントが生まれることもあるため、小規模なテストマーケティングを行い、可能性を探ります。
まとめ
STP分析は、限られたマーケティングリソースを最大限に活用し、効果的な戦略を構築するための強力なフレームワークです。
市場を細分化し、最適なターゲットを選定し、効果的なポジショニングを構築することで、競争優位性を確立できます。
本記事で解説したように、STP分析は体系的な手順に従って実施することで、より精度の高い成果を得ることができます。
特に日本市場においては、消費者の価値観や行動パターンが多様化しており、「すべての人に向けた」マーケティングではなく、特定のセグメントに焦点を当てた戦略がますます重要になっています。
STP分析の成功のポイントは、データに基づく客観的な分析と、顧客インサイトを融合させることです。
数値データだけでなく、顧客の「なぜ」を理解することで、より深い洞察を得ることができます。
また、一度確立したSTP戦略も市場環境の変化に応じて定期的に見直し、継続的な改善を図ることが重要です。
市場のダイナミクス、顧客ニーズの変化、競合状況の変化に敏感に対応することで、長期的な競争優位性を維持できます。
agsでは、eコマース関連のサポートをまるっとお任せいただけます。
課題分析や戦略立案、制作から広告配信・運用までECの売上拡大を目指し、一気通貫でサポートいたします。
また、「一律で広告費マージン型モデル」をやめ、成果最大化のために考えられた費用設定でコストを抑えてお客様の利益拡大にフルコミットします。
STP分析を活用したマーケティング戦略の構築にご興味があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
FAQ:よくある質問
Q1: 小規模企業でもSTP分析は有効ですか?
A1: はい、むしろ小規模企業こそSTP分析が重要です。
大企業に比べてリソースが限られている小規模企業は、市場全体に訴求するのではなく、特定のセグメントに集中する集中戦略が効果的です。
強みを活かせるニッチな市場に特化することで、限られたリソースを最大限に活用できます。
例えば、地域特化型のサービスや特定の趣味に特化した商品など、大企業が十分にカバーしていない領域に集中することで競争優位性を確立できます。
Q2: STP分析の結果をどのようにチームや社内で共有し、活用すればよいですか?
A2: STP分析の結果を効果的に共有・活用するには、まず視覚的なフォーマットにまとめることが重要です。
ターゲットペルソナの作成(具体的な顧客像の詳細描写)、ポジショニングマップの視覚化、コンパクトなエグゼクティブサマリーなどを用意しましょう。
次に、部門横断のワークショップを開催し、マーケティングだけでなく、商品開発、営業、カスタマーサポートなど関連部門の理解と協力を得ることが重要です。
全員が同じターゲットとポジショニングを理解していることで、一貫した顧客体験の提供が可能になります。
また、定期的な進捗レビューミーティングを設定し、STP戦略に基づいた施策の効果測定と改善を継続的に行うことも大切です。
関連するブログ記事
カテゴリー