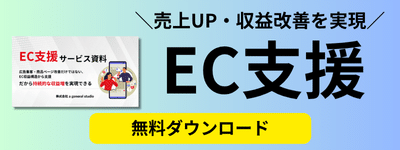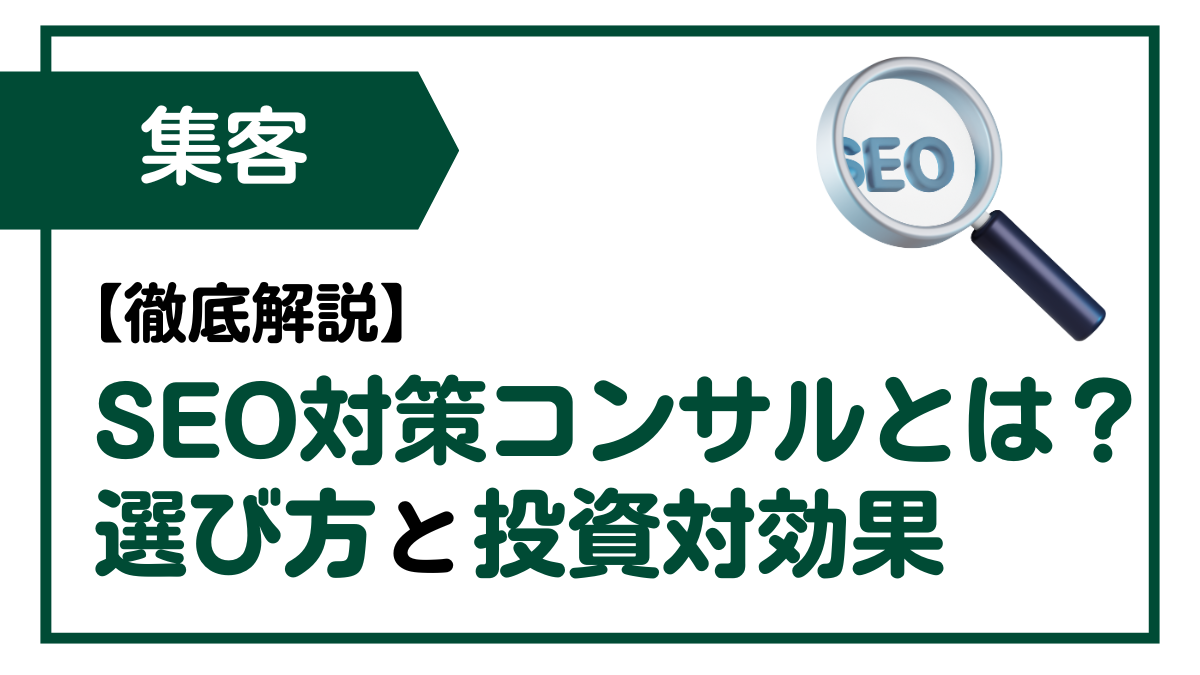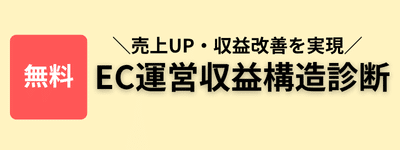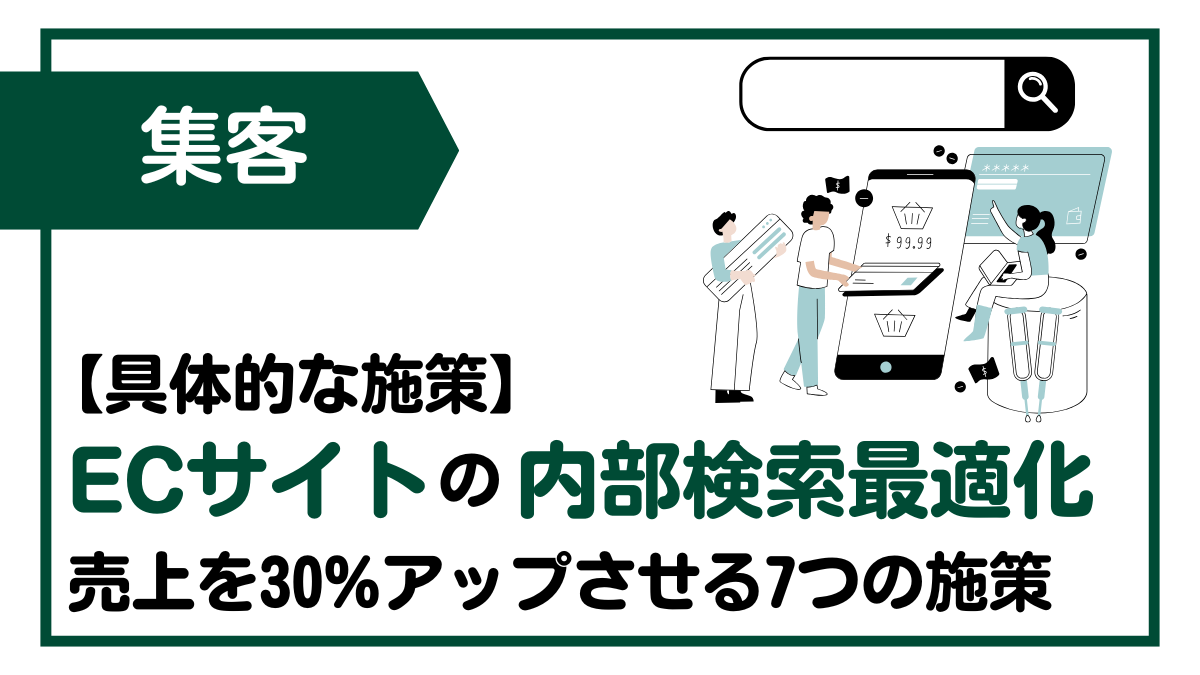
- SEO対策
ECサイトの内部検索最適化で売上を30%アップさせる7つの施策
目次
ECサイトを運営していると、ユーザーが目的の商品を見つけられずに離脱してしまう問題に頭を悩ませていませんか?
実はECサイトにおける内部検索は、売上に直結する重要な機能でありながら、最適化が不十分なケースが非常に多いのです。
内部検索の最適化が不十分なECサイトでは、ユーザーが求める商品を表示できず、大きな機会損失が発生しています。
本記事では、ECサイトの内部検索を最適化し、コンバージョン率と売上を向上させるための具体的な施策をご紹介します。
適切な内部検索の最適化を行うことで、ユーザー体験の向上だけでなく、売上を30%以上アップさせた事例も珍しくありません。
ECサイトの改善にお悩みの方は、eコマース専門のagsによる無料相談もぜひご活用ください。
ECサイト内部検索の重要性と現状の課題
内部検索の利用実態と売上への影響
ECサイトにおける内部検索機能の重要性は、多くの事業責任者が認識しているようで意外と見落としがちな要素です。
経済産業省の「電子商取引に関する市場調査」によると、ECサイト訪問者の約30%が内部検索機能を利用しており、その割合は年々増加傾向にあります。
さらに注目すべきは、内部検索を利用するユーザーの購入率が、利用しないユーザーと比較して平均2.7倍高いというデータです。
つまり、内部検索はただの便利機能ではなく、高い購買意欲を持ったユーザーが利用する重要な導線なのです。
一方で、バクスタ社の調査によれば、日本のECサイトの約65%で内部検索の最適化が不十分とされており、多くのサイトで改善の余地があることが明らかになっています。
特に問題となるのが「該当する商品がありません」と表示されるケースで、このようなゼロヒット率が高いサイトでは、検索利用者の直帰率が平均で58%にも達するというデータもあります。
ユーザーが直面する主な検索の問題点とその影響
ECサイトの内部検索において、ユーザーが直面する主な問題点とその影響について考えてみましょう。
まず最も多いのが、「検索しても目的の商品が表示されない」という問題です。
日本ネットショッパー協会の調査によると、ユーザーが内部検索で検索した際に、目的の商品が表示されない経験をしたことがある人は約78%にも上ります。
この問題が発生する主な原因としては、同義語や類義語、表記揺れ(「ジーンズ」と「デニム」、「スニーカー」と「運動靴」など)への対応が不十分なケースが挙げられます。
次に多いのが「検索結果の並び順が理解できない」という問題です。
検索結果が表示されても、関連性の低い商品が上位に表示されていたり、並び順のロジックが不明確だったりすると、ユーザーは混乱し、目的の商品を見つけるのに時間がかかってしまいます。
ECサイトに関する消費者調査では、検索結果の表示に不満を感じたユーザーの約62%が、そのサイトでの購入をあきらめた経験があると回答しています。
内部検索最適化がもたらす具体的なビジネスメリット
ECサイトの内部検索を最適化することで得られるビジネスメリットは多岐にわたります。
まず最も直接的な効果として、売上の向上が挙げられます。
EC業界の調査データによると、内部検索を適切に最適化したECサイトでは、売上が平均で30%向上したという結果が報告されています。
次に重要なのが、コンバージョン率の向上です。
内部検索を利用するユーザーは明確な購買意図を持っていることが多く、最適化によって適切な商品を表示できれば、購入に至る確率が大幅に高まります。
実際に、内部検索最適化に成功した国内アパレルEC企業では、検索利用者のコンバージョン率が2.3倍に向上したという事例もあります。
さらに、内部検索データは貴重なマーケティングインサイトの宝庫です。
ユーザーが何を検索しているかを分析することで、需要の高い商品カテゴリーや、カタログに不足している商品を特定できます。
これにより、品揃えの最適化や仕入れ戦略の改善につなげることができるのです。
ECサイトの内部検索最適化についてさらに詳しく知りたい方は、eコマース専門のagsによる無料相談をご利用ください。
こちらの記事でも詳しく解説していますので、合わせて参考にしてください。
検索機能の基本設計と改善ポイント
ユーザーフレンドリーな検索ボックスのデザインと配置
ECサイトの内部検索最適化において、最初に取り組むべきは検索ボックス自体のデザインと配置です。
Nielsen Norman Groupの調査によると、ユーザーはページを開いてから平均2.6秒以内に検索ボックスを探し始めるという結果が出ています。
最も効果的な配置位置はヘッダー部分の右上エリアです。
これはユーザーの視線の動きに関する研究(Fパターン、Zパターン)に基づいており、多くのECサイトでも採用されているスタンダードな位置です。
検索ボックスのサイズも重要な要素です。
モバイルでの使いやすさを考慮すると、横幅は画面の40〜60%程度を確保することが推奨されます。
デザイン面では、検索ボックスには必ず虫眼鏡アイコンを配置しましょう。
また、プレースホルダーテキスト(検索ボックス内に表示される薄い文字)は単に「検索」と表示するのではなく、「商品名・ブランド名で検索」のように具体的な指示を含めることで、ユーザーの行動を促進できます。
クリア機能(入力内容をワンタップで消去できるボタン)の実装も重要です。
特にモバイルでは、長い検索キーワードを一文字ずつ消去するのは煩わしいため、この機能があるとユーザー体験が大きく向上します。
検索アルゴリズムの基本と高度な検索機能の実装方法
ECサイトの内部検索最適化において、検索アルゴリズムは核となる重要な要素です。
検索エンジン技術協会の調査によると、高度な検索アルゴリズムを実装したECサイトでは、検索からの購入率が平均で45%向上したという結果も報告されています。
高度な検索機能を実装するための第一歩は、「あいまい検索」の導入です。
これにより、スペルミスや表記ゆれ(「ティッシュ」と「ティシュ」など)があっても、適切な商品を表示できるようになります。
同義語・類義語対応も重要な機能です。
例えば、「ジーンズ」と「デニム」、「スニーカー」と「運動靴」のように、異なる言葉でも同じ商品カテゴリを指す場合があります。
これには、同義語辞書を作成・メンテナンスする方法と、機械学習を用いて自動的に同義関係を学習させる方法があります。
検索クエリの形態素解析も有効なアプローチです。
日本語は英語と異なり、単語間にスペースがないため、「黒い長袖シャツ」という検索クエリを「黒い」「長袖」「シャツ」と適切に分解する処理が必要です。
また、検索結果のランキングアルゴリズムも重要です。
単純なキーワードマッチだけでなく、商品の人気度、在庫状況、マージン率やパーソナライズ要素を組み合わせたスコアリングシステムを構築することで、ユーザーの意図に沿った順序で商品を表示できます。
オートコンプリートと検索サジェストの効果的な実装
ECサイトの内部検索最適化において、オートコンプリートと検索サジェスト機能は、ユーザーの検索体験を大きく向上させる重要な要素です。
EC業界の調査によると、これらの機能を適切に実装したサイトでは、検索キーワードの入力完了率が約40%向上し、検索精度も平均で25%改善するという結果が報告されています。
オートコンプリート機能は、ユーザーがキーワードを入力し始めた時点で、入力途中の文字列に合致する候補を表示する機能です。
例えば、「スマ」と入力した時点で「スマートフォン」「スマホケース」などの候補を表示します。
表示する候補数は5〜7個程度に抑えることが重要です。
多すぎる候補はユーザーの選択を困難にし、かえって使いづらくなります。
検索サジェスト機能は、オートコンプリートよりも一歩進んだ機能で、ユーザーの入力内容に関連する検索キーワードを提案します。
例えば「スマートフォン」と入力した際に、「スマートフォン ケース」「スマートフォン 充電器」などの関連キーワードを表示します。
検索サジェストの内容は、サイト全体の人気検索キーワード、季節やトレンド、ユーザーの過去の検索・閲覧履歴に基づくパーソナライズの3つの観点から最適化することで効果が高まります。
こちらの記事でも詳しく解説していますので、合わせて参考にしてください。
検索結果の表示最適化と分析改善
検索結果ページのデザインと商品表示の最適化
ECサイトの内部検索最適化において、検索結果ページ(SERP)のデザインと商品表示方法は、ユーザーの購買決定に大きな影響を与えます。
ECコンサルティング会社の調査によると、検索結果ページの最適化によって、コンバージョン率が平均35%向上したという結果も報告されています。
まず重要なのは、検索結果の表示速度です。
Google社の研究によれば、ページの読み込み時間が1秒から3秒に増加すると、直帰率は32%上昇するとされています。
内部検索の結果ページも同様で、理想的な表示時間は1秒以内です。
検索結果の表示形式も重要な要素です。
日本のECユーザーの行動分析によると、アパレルなどのビジュアル重視の商品カテゴリではグリッド表示が効果的である一方、家電や書籍などのスペック比較が重要なカテゴリではリスト表示の方がコンバージョン率が高いという結果が出ています。
商品情報の表示内容も最適化のポイントです。
検索結果ページでは、ユーザーの購買決定に必要な最低限の情報(商品名、価格、主要な特徴、レビュー評価、在庫状況など)を簡潔に表示することがベストプラクティスとされています。
こちらの記事でも詳しく解説していますので、合わせて参考にしてください。
ゼロヒット対策と代替商品提案の戦略
ECサイトの内部検索において、最も避けたい状況の一つが「ゼロヒット」です。
これはユーザーが検索したにもかかわらず「該当する商品がありません」と表示される状態で、EC業界データによると、ゼロヒットに遭遇したユーザーの約70%がサイトを離脱するという深刻な問題です。
効果的なゼロヒット対策は、ECサイトの内部検索最適化において極めて重要な要素となります。
まず実施すべきは、ゼロヒットの原因分析です。
検索ログを分析し、スペルミスや表記ゆれ、同義語・類義語の問題、取り扱いのない商品の検索、在庫切れの商品、季節商品などのパターンに分類することから始めましょう。
これらの分析結果に基づき、それぞれの原因に対応した対策を実施します。
スペルミスや表記ゆれには「もしかして:〇〇」という形で正しいキーワードを提案する機能が効果的です。
例えば「マスカル」という検索に対して「もしかして:マスカラ」と提案し、クリックするだけで正しい検索結果に誘導する仕組みを構築します。
取り扱いのない商品の検索に対しては「類似の商品」や「代替となる商品」を提案するアルゴリズムを実装することで、ユーザーの購買意欲を維持できます。
国内の大手アパレルECサイトでは、これらのゼロヒット対策を実施することで、検索からの売上が約27%向上したという事例もあります。
ECサイトの内部検索最適化でお悩みなら、agsの無料相談をご活用ください。
検索データ分析と継続的な改善プロセスの構築
ECサイトの内部検索最適化において、検索データの分析と継続的な改善プロセスの構築は、長期的な成功の鍵となります。
デジタルマーケティング協会の調査によると、検索データを定期的に分析し、改善サイクルを回しているECサイトは、そうでないサイトと比較して年間売上成長率が平均15〜20%高いという結果が報告されています。
まず取り組むべきは、包括的な検索分析ダッシュボードの構築です。
検索利用率、検索コンバージョン率、検索離脱率、平均検索回数、人気検索キーワードのランキング、ゼロヒット率、ゼロヒットキーワードのランキングなどの指標をリアルタイムで確認できる環境を整えましょう。
これらの指標を定期的に分析することで、内部検索の問題点や改善機会を特定できます。
例えば、特定のキーワードでのゼロヒット率が高い場合、同義語辞書の追加や商品データの見直しが必要かもしれません。
また、検索キーワードの傾向分析は、マーケティング戦略の改善にも役立ちます。
急上昇している検索キーワードを特定することで、トレンドをいち早く捉え、在庫戦略や販促施策に活かせます。
まとめ
本記事では、ECサイトの内部検索最適化について、基本的な重要性から具体的な実装方法、さらには効果測定や改善プロセスまで幅広く解説してきました。
内部検索の最適化は、単なるサイト改善ではなく、直接的な売上向上につながる重要な施策です。
30%以上の売上アップを実現した事例もある通り、そのポテンシャルは非常に大きいと言えるでしょう。
最適化を進める際には、まず現状分析からスタートし、検索ボックスのデザインや配置、検索アルゴリズムの改善、オートコンプリートや検索サジェストの実装、検索結果ページの最適化、ゼロヒット対策など、段階的に取り組むことが重要です。
また、継続的な検索データの分析と改善サイクルの構築により、長期的な成功を実現することができます。
eコマース市場の競争が激化する中、ユーザー体験の向上と売上拡大を同時に実現できる内部検索最適化は、ECサイト運営者にとって最優先で取り組むべき施策の一つと言えるでしょう。
agsではeコマース関連のサポートはまるっとお任せ!
課題分析や戦略⽴案、制作から広告配信・運⽤までECの売上拡大を目指し、一気通貫でサポートいたします。
成果最大化のために考えられた費用設定でコストを抑えて利益拡大にコミットします。
ECサイトの内部検索最適化についてさらに詳しく知りたい方、具体的な導入をご検討の方は、ぜひagsの無料相談をご利用ください。
よくある質問
Q: 内部検索の最適化には、どのくらいの期間とコストがかかりますか?
A: 内部検索の最適化にかかる期間とコストは、現状のECサイトの規模や使用しているプラットフォームによって大きく異なります。
基本的な最適化(検索ボックスのデザイン改善、単純なアルゴリズム調整など)であれば、1〜2ヶ月程度の期間と比較的少ないコストで実施可能です。
一方、高度な最適化(AI活用した検索エンジンの導入、パーソナライズ機能の実装など)の場合は、3〜6ヶ月程度の期間と、それなりの投資が必要になります。
ただし、内部検索の最適化による売上向上効果は通常1年以内にコストを回収できるレベルであり、長期的に見れば非常に高いROIが期待できる施策です。
Q: 内部検索の最適化を外部ツールで行うべきか、自社開発すべきか、判断基準はありますか?
A: この判断はECサイトの規模や社内リソース、予算などによって異なりますが、一般的には以下の基準が参考になります。
外部ツール(Algolia、Elasticsearchなど)の利用が適している場合: ・月間訪問者数が10万人を超えるような中〜大規模ECサイト ・社内にエンジニアリングリソースが限られている ・迅速に導入したい ・検索機能の拡張性や柔軟性を重視している
自社開発が適している場合: ・非常に特殊な商品カタログや検索ロジックが必要 ・長期的に見て自社ノウハウとして蓄積したい ・社内に十分なエンジニアリングリソースがある ・将来的に非常に高度なカスタマイズを予定している
多くの場合、初期段階では外部ツールを活用し、成長に合わせて自社開発への移行を検討するというアプローチが現実的です。
関連するブログ記事
カテゴリー