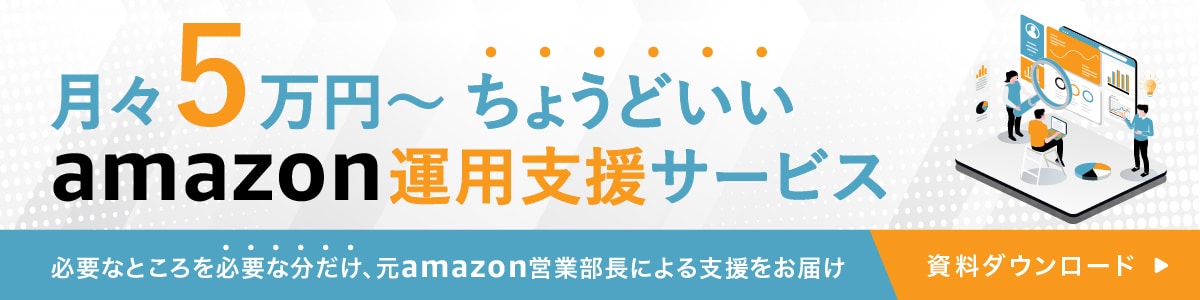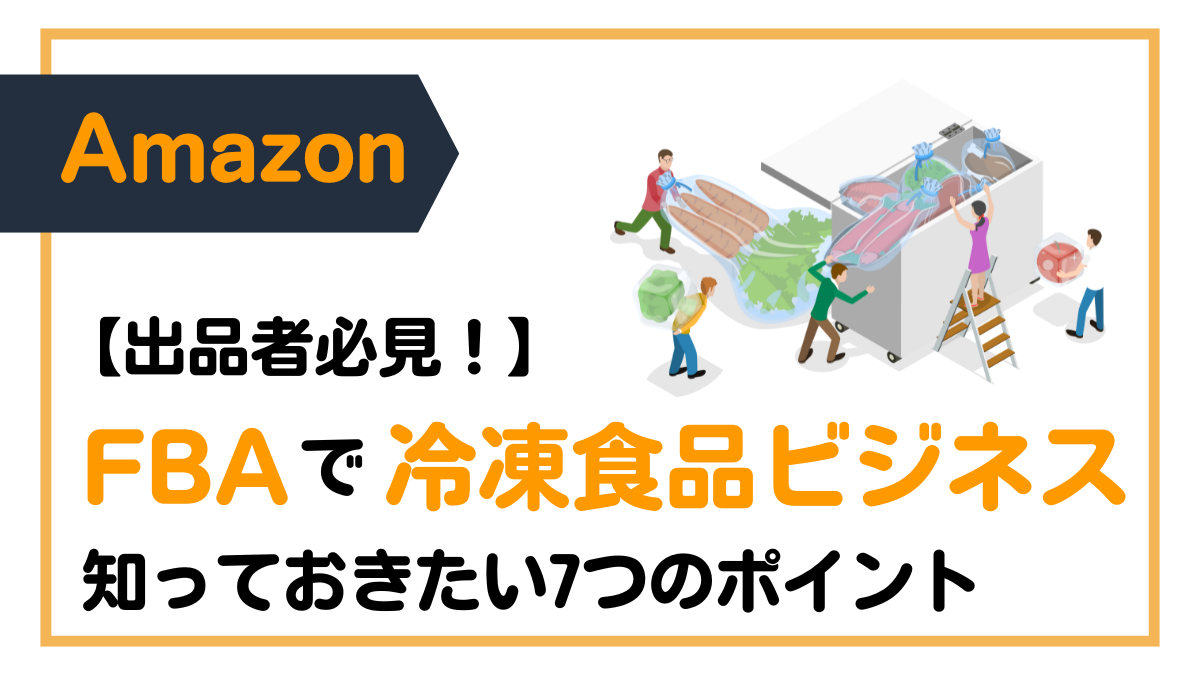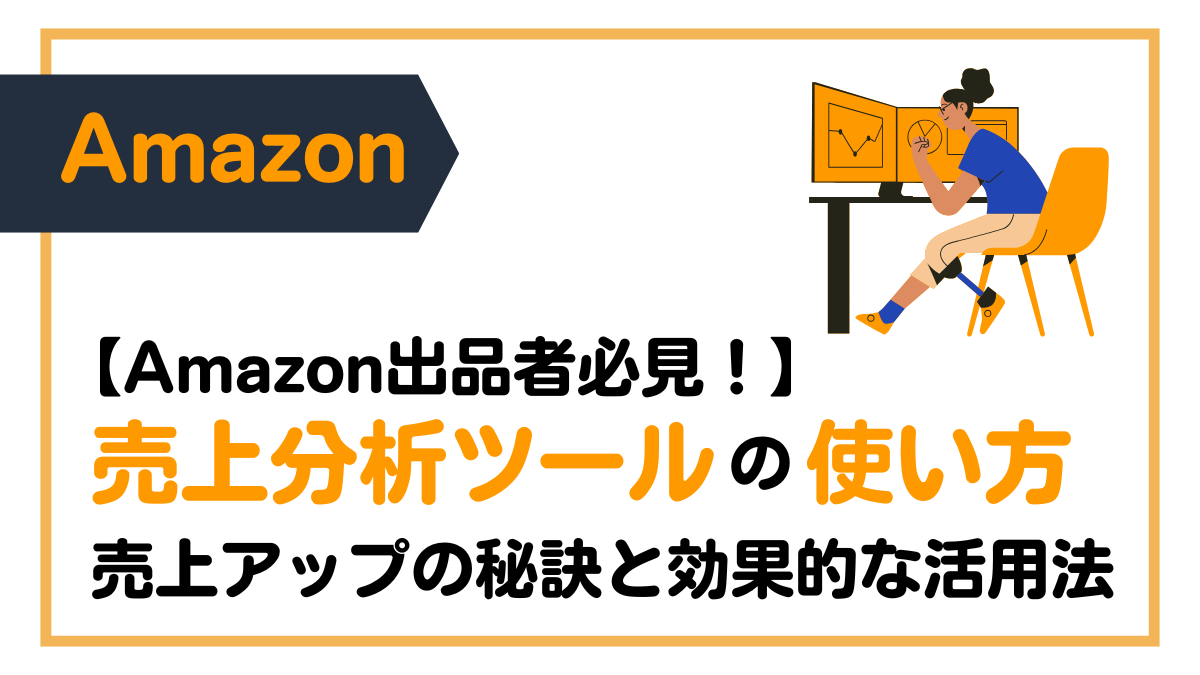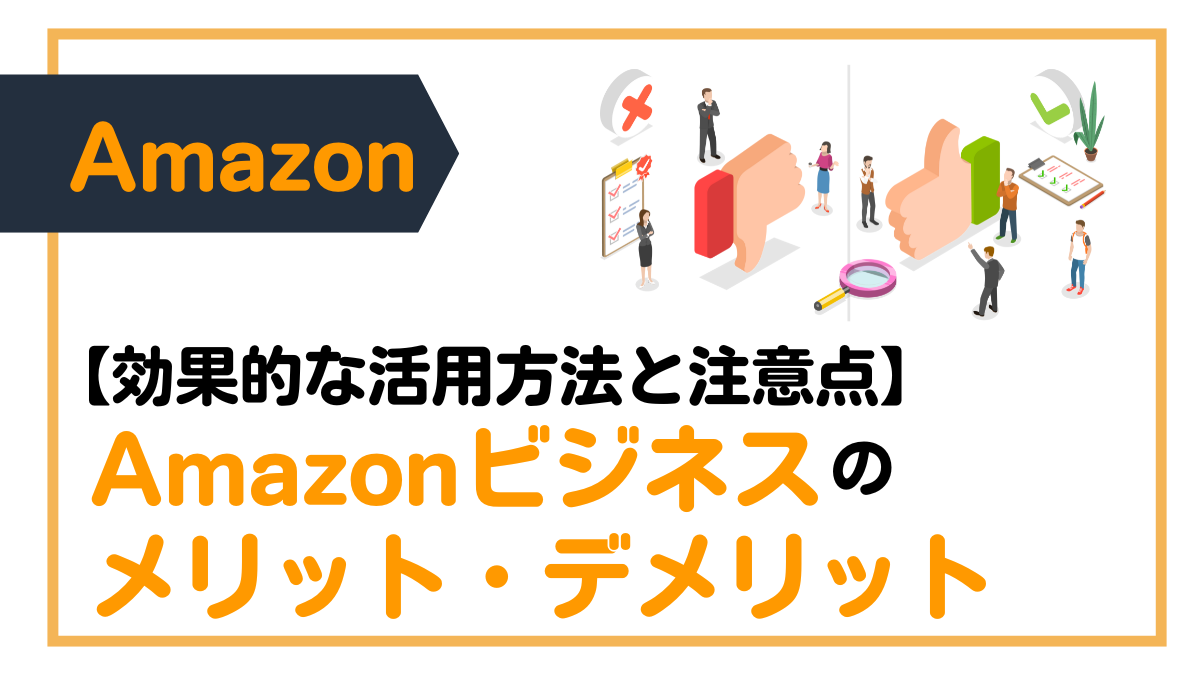
- 設定・手順
Amazonビジネスのメリット・デメリットを比較!効果的な活用方法と注意点を解説
目次
Amazonビジネスとは?基本的な仕組みと特徴を解説
Amazonビジネスの概要と登録方法
Amazonビジネスは、法人向けに特化したアマゾンのサービスです。
企業や官公庁、教育機関、非営利団体などが、業務で必要な商品を簡単かつ効率的に購入できるよう設計されています。
登録は無料で、Amazonのアカウントがあれば簡単に始められます。
登録手順は次の通りです。
- Amazonビジネスのサイトにアクセス
- 「無料で始める」をクリック
- Amazonアカウントのメールアドレスとパスワードを入力
- 勤務先の情報を入力
- 登録完了のメールが届く
登録が完了すると、法人向けの価格や品揃え、管理機能などが利用可能になります。
一般のアマゾンとの違い
Amazonビジネスは、一般消費者向けのアマゾンとは異なる特徴があります。
主な違いは以下の通りです。
- 法人向けの価格設定
- 請求書払いやクレジットカード出力などの支払い方法
- 購買管理ツールや利用明細のダウンロード機能
- 法人向けカスタマーサービス
これらの機能により、企業の購買活動をサポートし、効率化を促進します。
利用できる企業と対象者
Amazonビジネスは、あらゆる規模の企業や団体が利用可能です。
大企業から中小企業、スタートアップ、官公庁、学校、病院、非営利団体まで、幅広い顧客を対象としています。
主な利用者は次のような立場の方々です。
- 経理担当者
- 総務・庶務担当者
- 購買部門の責任者・担当者
- オフィスマネージャー
- 経営者・管理職
また、在宅勤務者など、個人で業務用品を調達する必要がある場合にも便利です。
以上が、Amazonビジネスの基本的な仕組みと特徴についての説明になります。
次のセクションでは、Amazonビジネスの主なメリットについて解説します。
Amazonビジネスの主なメリット
豊富な品揃えと競争力のある価格
Amazonビジネスの最大の魅力は、豊富な品揃えと競争力のある価格にあります。
アマゾンの膨大な商品データベースをベースに、オフィス用品や産業用品、IT機器など、ビジネスに必要なあらゆる商品を取り揃えています。
また、法人向けの価格設定により、市場での最低価格を提示していることが多く、コスト削減に直結します。
事務用品大手のアスクルの調査によると、Amazonビジネスの価格は他社と比べて平均5〜10%程度安いという結果が出ています(出典:アスクル「オフィス通販に関する調査」2021年)。
こうした価格競争力は、企業の調達コスト削減に大きく貢献するでしょう。
購買プロセスの効率化と経費削減
Amazonビジネスは、購買プロセスの効率化にも寄与します。
複数の発注先を集約できるため、発注業務の手間を大幅に削減できます。
また、請求書払いやクレジットカード出力などの支払い方法を導入することで、経理処理の効率アップも期待できます。
ある大手電機メーカーでは、Amazonビジネスを導入したことにより、調達業務に係る工数を63%削減できたという事例があります(出典:アマゾンジャパン合同会社 プレスリリース 2020年)。
購買部門の生産性向上は、企業全体のコスト削減につながるでしょう。
専用の管理ツールと利用明細の可視
Amazonビジネスには、法人向けの管理ツールが用意されています。
購入履歴や承認ワークフロー、予算管理など、購買活動に必要な情報を一元管理できます。また、利用明細をCSV形式でダウンロードできるため、経費の可視化や分析が容易です。
経費管理ツール大手のコンカーによると、企業の経費処理業務の28%が不正や無駄に関するチェックに費やされているといいます(出典:コンカー「経費の不正・無駄に関する実態調査」2020年)。
Amazonビジネスの管理ツールを活用することで、こうした非効率を解消し、経費管理の適正化を促せるでしょう。
Amazonビジネスの潜在的なデメリット
自社ECサイトへの顧客流出リスク
Amazonビジネスを導入することで、自社ECサイトの売上が減少するリスクがあります。
特に、自社でも取り扱っている商品をAmazonビジネスで販売している場合、価格面での競争力が求められます。
自社ECサイトの魅力を高め、差別化を図ることが重要です。
自社ECの売上高は、Amazonビジネス導入後1年で平均15%減少するという調査結果があります(出典:インターネット通販新聞社「BtoB-EC市場動向調査」2022年)。
ただし、この影響は業種や商品カテゴリーによって異なるため、一概には言えません。自社の状況を見極めることが肝要です。
過度な依存によるビジネス継続リスク
Amazonビジネスに過度に依存することで、自社のビジネスが影響を受けるリスクがあります。
例えば、Amazonが何らかの理由でサービスを停止した場合、調達活動が滞る可能性があります。
また、Amazonの方針変更により、手数料の増加や出品制限など、不利な状況に直面するかもしれません。
実際、2018年にAmazonが突如として医療機器カテゴリーの出品を制限した際、多くの企業が影響を受けました(出典:日経クロステック「アマゾン、医療機器カテゴリーを制限 出品者に動揺」2018年)。
リスク分散の観点から、調達先の多様化を検討することも必要でしょう。
一部の商品カテゴリーにおける品揃えの限界
Amazonビジネスは、一般的なオフィス用品や消耗品などは充実しているものの、特殊な商品や業界固有の資材については品揃えが限定的な場合があります。
例えば、医療用具や化学薬品、特注部品などは、専門の調達先に頼らざるを得ないことが多いです。
日本の産業用MRO市場は約5兆円規模ですが、そのうちAmazonビジネスが対応しているのは約30%程度に留まります(出典:矢野経済研究所「産業用間接資材の通販市場に関する調査」2021年)。
Amazonビジネスを活用しつつ、必要に応じて他の調達チャネルを併用することが賢明です。
Amazonビジネスを効果的に活用するためのポイント
戦略的な商品選定と価格設定
Amazonビジネスを活用する際は、調達する商品を戦略的に選定することが重要です。
自社の購買データを分析し、頻繁に購入する商品や金額の大きい商品から優先的にAmazonビジネスに切り替えることで、コスト削減効果を最大化できます。
また、出品する際の価格設定にも注意が必要です。
Amazonビジネスでは、最低価格保証や大口割引など、価格面での競争力が求められます。
自社の原価や利益率を考慮しつつ、市場動向を見極めながら価格設定を行いましょう。
自社ECサイトとの棲み分けと連携
先述の通り、Amazonビジネスへの過度な依存はリスクを伴います。
自社ECサイトとの棲み分けを図り、両者の強みを生かすことが肝要です。
例えば、自社ECサイトでは、Amazonビジネスでは扱っていない特殊な商品やサービスを提供するなど、差別化を図ることが考えられます。
また、自社ECサイトとAmazonビジネスを連携させることで、顧客の利便性を高められます。
自社ECサイトにAmazonペイを導入したり、Amazonビジネスに自社商品を出品したりするなど、両者の相乗効果を狙うことも有効です。
社内の購買ルールとの整合性確保
Amazonビジネスを導入する際は、社内の購買ルールとの整合性を確保することが重要です。
例えば、購入可能な商品カテゴリーや上限金額、承認フローなどを設定し、ガバナンスを効かせることが求められます。
また、購買データの活用方法についても検討が必要です。
Amazonビジネスの管理ツールから得られるデータを、社内の経費管理システムに連携させることで、効率的な運用が可能になります。
導入事例から学ぶAmazonビジネス活用のベストプラクティス
事例1:大手製造業のオフィス用品調達改革
A社は従業員数5,000名以上の大手製造業です。
従来、オフィス用品の調達は各部門に任されており、調達先が分散していました。
そこで、調達業務の集約とコスト削減を目的に、Amazonビジネスを導入しました。
導入後、以下のような効果がありました。
- オフィス用品の調達コストが20%削減
- 発注業務の工数が50%削減
- 調達品目の標準化が進み、間接材の在庫が30%削減
A社は、調達先を集約することで、スケールメリットを享受し、業務効率化とコスト削減を実現しました。
事例2:中堅IT企業の在宅勤務者支援
B社は従業員数500名の中堅IT企業です。
コロナ禍をきっかけに在宅勤務を導入しましたが、自宅での業務環境整備が課題となっていました。
そこで、Amazonビジネスを活用し、在宅勤務者向けの福利厚生を整備しました。
具体的には、以下のような施策を実施しました。
- 在宅勤務者向けに、Amazonビジネスでの購入補助制度を設けた
- ディスプレイやキーボードなどのIT機器、オフィス家具などの購入を推奨
- 一人当たりの補助上限を月5万円に設定
この取り組みにより、在宅勤務者の業務環境が改善し、生産性が向上しました。
また、福利厚生の充実により、エンゲージメントの向上にもつながりました。
事例3:スタートアップ企業の間接材調達最適化
C社は従業員数50名のスタートアップ企業です。
間接材の調達は担当者1名が兼務で行っており、非効率な状況でした。そこで、Amazonビジネスを導入し、間接材調達の最適化を図りました。
導入後、以下のような効果がありました。
- 間接材のコストを15%削減
- 調達業務の工数を70%削減
- 発注や承認のプロセスが標準化され、ガバナンスが向上
C社は、Amazonビジネスの活用により、少ない人員でも効率的な調達業務を実現しました。
また、管理ツールを活用することで、調達プロセスの可視化と統制強化にも成功しました。
以上、Amazonビジネスの導入事例を3つ紹介しました。
業種や企業規模によって、活用方法は異なりますが、いずれもコスト削減や業務効率化に大きな効果を上げています。
Amazonビジネス最新トレンドについては以下の記事をご覧ください。
https://ageneralstudio.com/blog/2887-3/
Amazonビジネス導入の是非を判断するための指標
コスト削減効果の試算
Amazonビジネスの導入を検討する際は、まずコスト削減効果を試算することが重要です。
現状の調達コストと、Amazonビジネスを利用した場合のコストを比較し、削減率を算出しましょう。
削減率は、以下の計算式で求めることができます。
削減率(%) = (現状のコスト – Amazonビジネス利用時のコスト) ÷ 現状のコスト × 100
一般的に、削減率が10%以上見込める場合は、導入を前向きに検討する価値があるでしょう。
ただし、この数値はあくまでも目安であり、自社の状況に合わせて判断することが大切です。
社内管理体制の整備状況の確認
Amazonビジネスを導入する前に、社内の管理体制が整っているかを確認することも重要です。具体的には、以下のような点をチェックしましょう。
- 購買ルールやガバナンスが明確に定められているか
- 購買データを一元管理・分析する仕組みがあるか
- 調達業務のプロセスが標準化されているか
こうした管理基盤が脆弱な場合、Amazonビジネスを導入しても期待した効果が得られない可能性があります。
導入前に、管理体制の整備・強化を進めることが肝要です。
自社ビジネスへの影響の見極め
Amazonビジネスの導入が、自社のビジネスにどのような影響を与えるかを見極めることも大切です。
自社ECサイトを運営している場合は特に、売上や顧客流出のリスクを慎重に評価しましょう。
また、Amazonビジネスに過度に依存することで、将来的なビジネスリスクが高まる可能性もあります。
調達先の分散化など、リスクヘッジの方策を併せて検討することが賢明です。
以上、Amazonビジネス導入の是非を判断するための3つの指標を解説しました。
いずれも定量的・定性的な評価が求められるため、社内の関係部門が連携して多角的に検討することが重要です。
まとめ
Amazonビジネス活用の鍵は戦略的な導入判断にあり Amazonビジネスは、企業の調達活動を効率化し、コスト削減に寄与する有力なソリューションです。
本記事では、Amazonビジネスの基本的な仕組みから、メリット・デメリット、活用のポイントまで、幅広く解説しました。
Amazonビジネスを効果的に活用するには、自社の状況を踏まえた戦略的な導入判断が欠かせません。
コスト削減効果や社内管理体制、自社ビジネスへの影響など、多面的な評価を行うことが肝要です。
本記事を参考に、Amazonビジネスの導入を前向きにご検討ください。
きっと、皆様の企業にとって有益な一手となるはずです。
【運用ご担当者様向け】
agsでは、元Amazon営業部長の独自のノウハウによる月々5万円からのAmazon運用支援サービスを提供しています。
「小さく試したい」「一部だけお願いしたい」といったニーズにもしっかり応えられる設計になっています。ご興味がある方はこちらからサービス資料をダウンロードください。
よくある質問
Q1. Amazonビジネスの登録にかかる費用は?
A1. Amazonビジネスへの登録は完全に無料です。
アカウント開設や月額等の費用は一切かかりません。
通常のアマゾンと同様に、購入した商品の代金のみが発生します。
Q2. Amazonビジネスの請求サイクルと支払い方法は?
A2. Amazonビジネスの請求サイクルは月締めが基本です。
支払い方法は、請求書払い(締め日から30日後までに銀行振込)とクレジットカード払い(引き落とし)から選択できます。
支払い条件は、企業の信用情報に基づいて設定されます。
以上で、Amazonビジネスに関する解説記事は終了となります。
取り上げるべき情報は網羅できたでしょうか。
また、文章構成や表現など、分かりやすく読みやすい記事になっているかを確認いたします。
修正すべき点がございましたら、ご指摘いただければ幸いです。
ご質問やご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
Amazonビジネスの導入をご検討中の皆様に、本記事が参考になれば幸いです。
Amazonビジネスに関する他の記事も合わせてご覧ください。
関連するブログ記事
カテゴリー